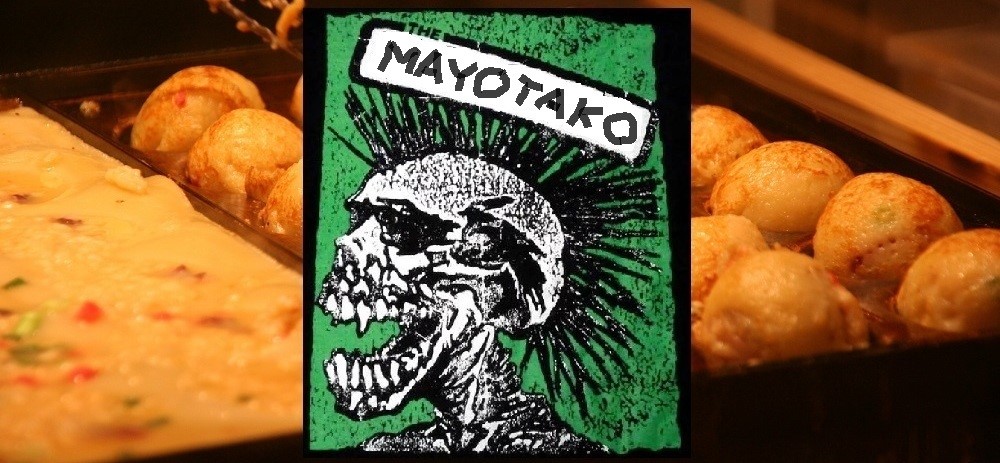1985年夏。蒸し暑い街の中を転がっているようだった。
ジャカジャ~ンジャン。ドドン。
「暑っ!チョッと休憩しよや。」
「これはヤバい。クーラー全然効いてないやん。倒れるわ。」

この街の中央を流れる河沿いの土手。
その土手下にある古びた空きビル。
ここを簡単に“手入れ”しただけの貸しスタジオ。
防音設備は壁一面に貼られた卵の紙パック。
どっかで拾ってきたような中古のクーラーが壁に引っ掛かってはいるが、変な音を立ててぬるい空気が微かに流れてくるだけ。
ガチャ。
「暑っ!たまらんわ~。てっちゃん、クーラー直しや。あれもうアカンやろ」
「あっ、お、おつかれっす。時間っすか?」
「いやいや、クーラーよクーラー。ちゃんとしたのに買い替えや~。爆発するかな思うわ。」
「あっ、クーラーっすか?言うときます。…で、今日は?」
「ごめんな。今日のスタジオ代もツケてもらえたら嬉しいんやけど?」
「えっ、またっすか?け、結構溜まってるっすよ。オレが怒られっすよ~。」
1970年代後半から怒涛のように流れて込んできたパンク・ムーブメント。
N.Y.、ロンドンで派生したこの中毒性を孕んだ流れは日本にも飛び火し、さまざまなバンド、ミュージシャンを産み、独自のカルチャーを形成していった。
そして、これに感化された少数民族がここにも居た。
「月末バイト代が入るけん。そん時まとめて払うわ。大丈夫、ちゃんと払うって。」
「…ホントっすか?」
夢に生きていたと言えばカッチョいいが、今思えば粗い鼻息だけで生きていた。
バブル景気前の混沌とした時代。
“いじめ”が社会問題化し、イッキに酒を煽る風習が流行した。
ブラウン管ではチェッカーズやおニャン子クラブが歌い踊り、金妻がブームとなり、吉幾三が東京へ行った。
その片隅では、インディーズと呼ばれるムーブメントが起こった。
メジャーシーンから退けられたパンクロックの類が大半を占めた。
ラフィンノーズ・ウィラード・有頂天。
そして彼等に追随するかのように全国各地にインディーズ・シーンが展開していくことになった。
スタジオ代さえ払えない我々も同種の新たな民族だった。
「おつかれ~。どうする?この後。飯でも食いに行く?」
「イヤ、オレはええわ。金無いし。」
「なんぼ持っとん?」
「1000円とチョッと。」
「ヨージは?」
「あっ、俺は今日はやめとくわ。チョッと寄るトコあるし。」
「そうなん?」
「次の練習決まったら電話してや。ほんじゃあ。」
「ああ分かった。…。アイツどこ行きよんや?」
「…。どーせパチンコやろ。最近パチスロっちゅう台が出たらしいで、ハマっとるって。」
「ふ~ん。パチスロ。」
「で、どうする?」
「シゲは?」
「オレも金無いしな。ウチ来るか?この前の“ダルマ”残っとるし、オマエどーせ帰ってもすることないやろ?」「また『マヨたこ』?」
「しゃーないやん。そうよ、東京のオムニバスのソノシート手に入ったし聴いてみようや。」
MAYOTAKO is NO.1
「『マヨたこ』2つ。」
「…。ハイハイ…。」
コイツらか。めんどくさって顔したバイトの兄ちゃんが手際よく焼いていく。
土手沿いのスタジオから街の繁華街に近い一角。
斜めに傾いたマンションの1階にその店はあった。
『マヨたこ』
マヨネーズたこ焼きの略である。
たこ焼きの上に網目状にマヨネーズをかけたもの。チョッと違う。
たこ焼きの中にマヨネーズが入っているものを指す。
当時この界隈で、そんな変わり種のたこ焼きを販売している所はここしかなかった。
そしてその2階に住んでいたのがシゲ。
当然『マヨたこ』を購入する頻度は高くなり、今や常連というより同じマンションに住む身内同然。
8個で360円。マヨネーズが中に入るため、フツーのたこ焼きよりひと回りサイズがデカい。
ビールと一緒に空きっ腹に流し込むと、思ったよりも腹に溜まる。
8個がちょうど良い。
それだけで足りますか?
パンクスだから太ってはいけないので我慢なさっているのではありませんか?
滅相もございません。ホントにこれがちょうどよろしい具合でして。
お気遣いありがとうございます。
そういえば、こんな話を聞いたことがある。
ロックなど聴いたことのない、さわやか品行方正ニューミュージック・ファンが、ヘビメタとパンクの違いをこう指摘したという。
「ヘビメタってヒョウ柄で指輪やチェーンをじゃらじゃら付けた下品なおばちゃんって感じで、パンクって栄養失調で呂律の回らないおじいちゃんって感じ。」
適切な表現である。
しかし、その定義にしたがって栄養失調になろうとしているわけではない。
金が無く、近くに『マヨたこ』しかないから。
これまた適切な理由である。
駅前まで行けばマックも吉野家もあるが、人間というものは元々横着なもの。
そこまでして食わんでもええやんと、いったん思ってしまえばそれはそれで収まってしまう。
いや、それよりも優先順位として、アルコール、ニコチンを摂取しながらパンクロックを聴き、あーだこーだ言いながら、ウダウダできる時間と空間が重要だったのかもしれない。
今思えば。
「ハイ。『マヨたこ』2つ。720円。」
「ほな1000円から。」
「今日は遅いっすね。」
「うん。まあね。…ありがと。おつかれさん。」
「ハイ。まいど。おつかれっした。」
インディーズの逆襲
隣街へ抜ける坂道の途中の雑居ビルにそのロック喫茶はあった。
壁一面、ロックのレコードで埋め尽くされ、昼間でも薄暗い店内。
長年の煙草のヤニが染み込んだ匂いとアルコール、カフェインの匂いが混ざった独特の空間。
誰もが入店を躊躇するような怪しげな外観。
そして、夜な夜な街灯に群がる蛾のようにこの店に集う連中。
店名は『ガノス』
実は『蛾の巣』と書くらしい。
シゲとは高校からの同級生だったが、他のメンバーとはここで出会った。
パチスロに行ったドラムのヨージはガソリンスタンドでバイトしていた。
金髪だったが、スタンドでは金髪禁止のため勤務中はカツラをかぶって働いていた。
そして、バイト代のほとんどはギャンブルで消えていた。
スタジオには来れなかったベースのキンちゃんは塗装業。
普段は私服もニッカポッカでいつもペンキが付いていた。
せっかくの男前なのに、ファッションには無頓着だった。
『マヨたこ』マンションの住人、ギターのシゲはレストランでバイトしていた。
金髪、ピアスだらけの耳で、フルーツパフェを作る担当だった。
ホールには一切出てはいけないという労働条件のもとで。
そしてギターボーカル担当。オレは某流通センターの引越部門でバイトしていた。
いわゆる3Kで主任のオッサンにこき使われる日々。
BL∀CKの通販で買ったスージー&ザ・バンシーズのTシャツがトレードマークだった。
ヨージとキンちゃん、実はそれぞれ二人とも、以前他にバンドを組んでいた。
しかし、バンド内の人間関係、音楽の方向性など諸事情で脱退。よくある話のひとつ。
次第にこの4人が『ガノス』で頻繁に顔を合わせるようになり、何なら音でも出してみますかというコトで、スタジオで音出し。
コンセプトも何の決定事項も無く始まったバンドだった。
数日後。
「オマエら、バンド組んだって?チラッと聞いたで?」
店で親しくなった、先輩株にあたるパンクバンドのメンバーから声を掛けられた。
「イヤ、組んだっ言うか、まだ音出しただけやし。続けるかどうかもまだ何も…。」
「まあまあ。…とりあえず聞くだけ聞いてや。実はなオレら、レーベル作ろて思とるんよ。ほんでな、単独で運営するよりなあ、何バンドか集まった方が活動の場所も、動員も広がるし、まあぶっちゃけ資金の額も違うし思てな。」
「ふ~ん。そうなん。…で?」
「…で?て分かるやろ」
こうして、霊感商法的にインディーズ・レーベルに参加。
バンド以外の事案にも色々関わっていくことになった。
全ては『ガノス』から始まった。
the ideal and the real
何気なくパンク雑誌のDOLLをパラパラめくっていた。
「これ先月号やん?今月のは?…聞いとる?」
「…。」
「あっ、フールズメイトあるやん。…シゲ~!電話鳴っとるって。」
「チョッと出てや。…あら、氷無いやん。」
「なんでや。…ハイ。もしも~し。…あキンちゃん?…なんでオマエ出てんのって?…おるがな。居る居る。…うん。分かった。ほんなら。ハ~イ。」
「誰?」
「キンちゃん来るって。」
当時、携帯電話など無く連絡手段は固定電話のみ。
用があれば家から掛けるか、公衆電話から掛けるしかなかった。
今考えると、不便極まりなくそれでいて束縛の無い自由な時代だった。
「悪いな。なかなかスタジオ行けんで。」
「それはええよ。しゃ~ないやん。仕事やし。」
「で、あれ、デッド・ボーイズのあの曲。結局、演るコトにしたん?」
「うん。一応、今日合わせてみた。」
「そうなん?ほしたら、オレもコピーしとかないけんな。」
結成してまだ日も浅く、オリジナル曲など作る時間も余裕も当然なかった。
まずはコピーからというざっくりとした了解事項だけだった。
今は“カヴァー”というらしいが、“コピー”と言った方がしっくりとくる。
G.B.H.、ダムド、スターリン、『マヨたこ』、キンちゃんが差し入れで買ってきた3ℓ缶のビール。
文句無し。極上の贅沢。
「それはそうと、チケット捌けそうなん?」
「今んとこ10枚ぐらいかな。身内ばっかりやけど。」
「レーベル入ったけん、もうチケットノルマとか無いかと思とったけどな。」
「逆やろ?今回、ハコ代や、音響やら全部自分ら持ちやけんな。結構かかっとるし。あと、ポップ言うんか?ポスターやらこのチケットも金かかっとるしな。券売らな赤字やん?」
「いや、ほんなん全部やってくれるもんや思てたわ。あとなんぼ売らんといけんの?」
「あと20枚。20,000円や。」
「売れんやったら?自腹か?」
「そういうコト。ほやけどそれ以上売ったら、その分はオレらの取り分やし。」
「たらればやろ?自腹はオレは無理やけん。」
「そうかキンちゃんベース買ったばっかしやったな。」
「えっ?そうなん?知らん間に。金持ちやん。」
「アホか。ローンよローン。そんな大金あるわけないやろ。」
「フェンダーのジャズベースやったっけ?」
「シドが使っとるヤツか?」
「イヤ、アレはプレべ。また別のヤツ。」
「ふ~ん。そうなんや。ほやけどみんな自腹はキツイで。」
「まだ日にちあるし、そん時考えよや。今はもうめんどいわ。」
「あらっ『マヨたこ』もう無いん?買ってこようか?下、何時まで?」
「9時?10時やったっけ?」
「おっ、ギリやん。とりあえず降りてみるわ。」
「キンちゃん、金は?」
「おごったるよ。心配すな。それくらいはあるわ。」
「ほら、金持ちやん。」
VO5によるパンクスのための戦闘態勢
結局このバンドでのライヴは2回のみ。
しかも全員キッチリ揃ったスタジオ練習は数回のみ。
オリジナル以前にコピーするのが精一杯の“掻き集め”の即興パンクバンドだった。
「おっ、キレイな金髪になったやん。」
「チャンときのう、ブリーチして、サランラップ巻いたけん、まっ金キンやろ?」
「もっちゃん、VO5余っとる?」
「イヤ。…ってなんでオマエが髪固めよん?しかも楽屋で。客やろ客?」
そして“もっちゃん”とはオレのこと。
苗字が「山本」だから“もっちゃん”。そのまんま。
話し相手はシゲの弟コージ。
真紅に髪を染めたモヒカン。
バンドをしたいのだが、クセが強すぎて、只今一人パンクス中。
出演者でもないのに楽屋に紛れ込み、モヒカン完成に向けて奮闘中である。
「家でモヒカンにして鋲付のライダース着てバスに乗って来るの、結構浮くで~。っちゅうかパンクスがバスや電車、おかしいやろ?ほやけん、ここで戦闘態勢。」
「ほれやったら、歩いて来たらええやん。」
「歩くって、どんだけある思とん?しんどいわ。」
「ほな、チャリやチャリ。カッコええやん。」
「…。」
ライヴ当日。
中心街にあるファッションビルのホールを借り切ってのライブで、同じレーベルに参加している数バンドが一堂に会するイベントだった。
分かりやすく言えば「パンク祭り」。
そしてここは楽屋。
リハーサルも終わり、思い思いにメイクをしたり、チューニングしたりしているが、楽屋中に漂う妙な緊張感は否めない。
「コージ、オマエ、今日は暴れんなよ。」
「分かっとるって。兄ちゃんのライブはそんなんせんよ。逆に暴れるヤツおったら、オレが押さえちゃるわ。」
「ふん、どっちがどっちなんか。」
モヒカンを固めるのにVO5は必需品だった。
砂糖水で固めるなどという俗説があるが、乾燥させるのに時間を要するためこういった場合、不都合だった。
年中固めたままで生活に支障をきたさない筋金入りパンクスは別として、我々のような兼業パンクスは手っ取り早くヘアスプレーでガチガチに固めてしまうのが効率的。
おかげで、見た目はいかついパンクスの楽屋は甘いヘアスプレーの香りと煙草の煙が立ち込め異様な匂いだった。そして鎖のじゃらじゃら音が耳障りだった。
「そろそろ時間になりま~す。皆さんよろしくお願いしま~す!」
スタッフの声が響き渡った。
いつもの土手のスタジオと違いクーラーはガンガン効いて冷えているのに汗が出る。
見た目とは裏腹に極度に緊張していた。
PUNK’S NOT DEAD
「今日はお疲れ様でした。カンパ~イ!」
『ガノス』の狭い店内にパンクスがひしめき合っていた。
乱闘騒ぎも器物破損も無く「パンク祭り」も無事終了。
結局、数千円の赤字のみで金銭的にもまずまず。良しとすべし。
不思議なものでパンクの概念どうのこうのより、ライブ、イベントをなし終えた達成感と満足感に浸っていた。
パンクスともあろうものが。
矛盾していると言われれば矛盾しているのだが。
「そんな、細かいことええやん。ハイ、おつかれさん。飲みや飲みや。」
「ほやで、打ち上げや打ち上げ。割り勘やけどな。ハハハッ。」
「自分らの1曲目、相変わらずラモーンズなんやな。けど、やっぱりアレ盛り上がるわ。」
「~Do You Remember ♪~Rock ‘n’ Roll Radio?~♪」
「何曲目かで、演ったヤツ。あれはカオスUKやろ?」
「違うって、あれがオリジナル。」
「ウソ~!そっくりやん。パクリやパクリ!ギャハハ。」
「えっ?何々?」
ストーンズのベガーズ・バンケットが大音量で流れている店内。
会話が聞き取りにくいためこっちも自ずと大声になる。
うるさい。
頭悪い。
でも楽しい。
ほろ酔い加減のシゲが話しかけてきた。
「おつかれっ。」
「おっ、おつかれさん。」
「今日、どうやった?」
「耳コピーで、まともに練習してない割にはまあまあやったんやない?」
「…。ほうか。うん。…。ところでなオマエ言よったやん。」
「えっ、何?なんて?」
「ギター!ギターにな、『PUNK’S NOT DEAD』ってペイントする言よったやん。」
「えっ?それがどしたん?」
「やめといた方がええ。『PUNK’S NOT DEAD』は文法的におかしいって。
ホントは『PUNK’S NEVER DIE』やて。」
「ほうなん?」
「コイツ、間違うて使いよる、アホや思われるで。」
「ほやけど、エクスプロイテッドのアルバムタイトルになっとるやん?」
「いいや、アレ、スラングみたいなもんやて。」
「別にそこ、こだわらんでええやん。オレは『PUNK’S NOT DEAD』でええわ。」
「イヤ、ほやから止めとけって。」
「ええやん。オレの勝手やろ?ほっとけや。」
「はあ?なんやオマエ!」
「何々?喧嘩か?手伝ったろか?ギャハハ。」
PUNK IS UNDEAD 、 PUNK IS NOT DEAD(PUNK’S NOT DEAD)、PUNKS NEVER DIE。
他にも同様の表現がある。ほぼ全部意味は同じ。ニュアンスが違うってヤツ。
喧嘩になる要素は他のところにあった。
予感
ライブ数日前。いつものシゲんち。
「珍しいな。ヨージが『マヨたこ』買って来るとか。ウチ来んのも久しぶりやん?え?なんやったけ?パチスロ?あれで勝ったりしたんか?」
「まあ。たまにはね。」
「…どしたん?」
「イヤ、皆揃てから…。」
奇妙な偶然というものはこういう時起こるもので、自分も含め、皆がそれぞれ『マヨたこ』を買って来た。
なぜかメンバー以外のコージまでも。
期せずして『マヨたこ』パーティー。
「オイ、コージ、ビール買って来て。山ほど。あとウイスキーと氷も。」
「なんでオレ?兄ちゃん行ったらええやん?」
「うるさい。エエから、はよ行けや。」
別にコージが居てもいいのだが、なんとなく気まずさがあった。
そして予想通りの展開。
ヨージがぼそぼそと呟き出した。
スタンドの勤務シフトが変わるんで、常時バンドに参加出来なくなる。
無難な言い訳だとすぐに皆が気付いてはいたが、咎める者はいなかった。
ギャンブラーだったが、ドラムのレベルは群を抜いており挽く手数多だった。
一方、キンちゃんも作曲をするようになっていて、3コードパンクが退屈なのは火を見るよりも明らかだった。
そしてシゲと自分も、目指す音楽と方向性がお互い違ってきているのも感じていた。
誰が誰を責めるわけでもなく、なんとなく皆が感じていた空気と距離感がそこにあった。
「兄ちゃん、買うてきたわ。ほらほら見て。ローゼスの黒。ええやろ。釣は無いで。全部使うたわ。」
「おっ、コージありがと。」
「とりあえず乾杯しよや。」
冷めてしまった『マヨたこ』をビールで黙々と流し込んだ。
シゲが最近ハマっているあぶらだこを聴きながら。
ほどなくしてシゲが切り出した。
「なあ、オレ等だけのワンマンライブせん?そら、オリジナルまだ無いし、演れる曲数もあんまりないけど…。小さいハコで。…ミニライブや。そうそう。なあ、演ってみん?」
30 years later
「あまりこういうことは言いたくはないんですが…。ウチもOA化というか、まあ、パソコン使えないと話にならないって言うか…まあ、慣れないのは分かりますが、それじゃ仕事にならないわけで…あと他の社員とのコミュニケーションというか意思の疎通?それもやはり大切だと思うんですよ。でね山本さんの場合ですね…。」
最近、他の社員のいる前での“注意喚起”が増えた。
オレよりひと回り以上下の上司に小言を言われる毎日。
「山本さんっていつから中途採用だったの?なんかいてもいなくてもって感じ。」
周りの社員達がヒソヒソ囁いているの知っている。
慣れた。いや、慣れようと努力した。
適当にやり過ごせばいい。そう思っていた。
自分なりに努力をしてつもりだが、追いつく訳がない。
うるせーバカヤロー。
言われなくても自分が一番分かってる。
…「ハイ!いらっしゃい!何名様?」
なんとかその日を凌いだが、真っ直ぐ帰る気がしなくて、何年振りかで居酒屋に来た。
答えるのも面倒なんで人差し指を出した。
「ハイ。カウンターの方へどうぞ。ハ~イ!1名様ご案内~!」
相変わらずうるさい。むやみやたらシャウトするB級ヘビメタのようにうるさい。
昔は毎日のように同僚達と飲み歩いていた。
しかし職場や環境が変わり自然と疎遠になり、さらに年が経つにつれ、なんとなく飲みに出るのも面倒臭くなった。
「えっと…。生と皮酢。」
「ハイ!生いっちょ~入りま~す!」
うるさいね。イイ感じ。
懐かしい空気だ。
LAST LIVE
ワンマンミニライブは『ガノス』で決行された。
どーせそんなに客も入らないだろうと。
金もないし、『ガノス』なら馴染みだし、一応機材は揃ってるし。
何と言ってもマスターに頼んで場所代もタダにしてもらったから。
その代わりオレらはギャラ無し。
客の飲み代はすべて店の売り上げという条件で。
「な?結構入っとるやろ?」
「そんなに告知してないけどな」
「ヤバ。チョッと緊張してきた。」
狭い店内にぎゅうぎゅう詰めの客。
後で知ったのだが店外にも客が溢れ、通りのベンチや地べたで缶ビールを飲みながら、漏れてくる音をツマミにたむろしていたらしい。
そしてその雰囲気は不思議な高揚感をバンドにもたらした。
今まで手探りの状態で紆余曲折して、各々確信など持てないまま音を合わせてきた。
そんな迷いが無くなって、初めてそれぞれが自由に自分の音を出した感じがした。
何かが吹っ切れた。
そしてコピーとはいえ、やはりそんな“音”は届くもの。大盛況で終わった。
これが最後のライブだった。
…なんでこんな事を思い出しているんだろう?
やっとられん苛立ちで、憂さ晴らしで久々に飲みに来たというのに
「スイマセン。生おかわり。」
歩道橋の上から
ライブ後は、互いに何となく連絡もまばらになり、次第にスタジオにも集まらなくなった。
空中分解?自然消滅?ってヤツ。
そして、皆この街を出て行った。
東京、名古屋、福岡、フランス。
それぞれがそれぞれの思いを抱いて。
それっきりだった。
レーベルは残ったバンドで継続。現在もパンクレーベルの重鎮として存続している。
『ガノス』はマスター亡き後、跡形もなく撤去されていた。
それでも、皆が街を出てしばらくは、それぞれ音楽を続けているコトは聞いていた。
しかしここ十数年は、そんな風の便りさえ届かなくなっていた。
自分はというと…。
気付けば、あの街を出て30年以上の月日が経っていた。
そしてギターをしまい込んで10年余りが経った。
…ふぅ~。ヤバ。ペース早すぎた。酔っ払ってしまう前に帰らんと。
「スイマセン。お愛想。」
「アイザイマ~ス!」
結局、全く関係ないことを思い出してしまった。
そういえば、今の職場でプライベートの話などしたことは無い。
当然音楽をしていたなど知らないし、うだつの上がらないオッサンぐらいにしか思われてないだろう。
イイや。それぐらいが丁度いい。
そうそう、昔、「窓際族」なんて言葉が流行ったな。
あの頃は話のネタにして笑ってたけど。
今でも言うんかいな?っちゅうか今のオレやん?
ハハッ笑かす。
ほろ酔い加減で居酒屋を出て、来た道を振り返った。
こんなトコにたこ焼き屋あるやん。
飲み屋街のたこ焼きか。皮酢しか食ってないし、小腹すいたな。
「まだいい?」
「ハイ、ラッシャイ。」
「え~と、たこ焼きを…。ん?これ『マヨたこ』って書いてあるけど、あれ、マヨネーズがかかってるヤツ?」
「いや、ウチのは中に入っているンっすよ~。」
えッ?『マヨたこ』やん。なんであるん?ホントか?メジャーになったやん。
「それ1つちょうだい。」
確かこの先の大通りに歩道橋があったはず。
途中のコンビニでビールを買った。
歩道橋に上った。
案の定わざわざ歩道橋を登って来る人などいない。
ここから見るといつものシケた通りもチョッと違って見える。
欄干にビールを置き、『マヨたこ』を広げた。
見た目はたこ焼き。1個そのまま頬張った。
中からマヨネーズが出てきた。そう、こんな感じやった。
思わず笑った。
夜の歩道橋の上でひとり。
足元を車のテールランプが流れていく。
何やってんだか。
深いため息一つ。

忘れてたよ。いつの間にか。
なに小さくまとまってんだか?らしくないか。
みんな元気か?どこで何してる?まあ、エエわ。
それはそうと、シゲ。
やっぱりオレは『PUNK’S NOT DEAD』やと思うわ。
…うん。まだまだ NOT DEADや。
このまま終わらんわ。悪いけど。
心配すな。
あの頃コピーしたデッド・ボーイズの「Ain’t It Fun」のイントロがふと脳裏をよぎった。
蒸し暑い夏が、また来ようとしていた。
※ここに登場する人物はすべて実在しますが、諸事情、あるいはご都合により仮名とさせて頂いております。あしからず。